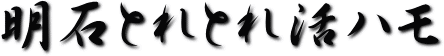
�i��g�ԋ�/�G�r�����j |
| �H�̃n���́A�u�c��n���v�Ȃ�Ă����܂����A ���˓��ł́A�~�ɔ����H�~�������ɂȂ��H���{�B�Ă��{�Ƃ����C���[�W�́A�������̉e�������������H�������A�H�͎��v�����Ȃ��Ȃ�̂ő���������肪���I�u�����낤�����낤�v�ł͂Ȃ��A��������������ɓ���܂��I���������̃n����Ȃ�Ă����ō��I |
 |
 |
 |
 |
 |
�����̂ڂ邱�ƍ]�ˎ���A�����̗l�ȗⓀ�ݔ��̂Ȃ�����B
�ď�͋��s�����^�Ԃ̂�����ł����B
�����Ŗڂ�t����ꂽ�̂������͂̋����n���B�u�n���Ȃ���v���낤�I�v���ƁB
���̌�A���s�ł̓n�������ɖ�����������A���ł͑S���I�ɂ��L���A�Ă̋_���Ղ̍��ɂ͈�C�Ɏ��v�����܂�܂��B����ȂƂ��납��Ă̋��Ƃ����C���[�W������܂��B
�ł��A�ق�Ƃ��ɉĂ��{�H
�Y�n�ł͂ǂ��H
���Ăɂ͋I�ɐ����������m�ɖʂ����Ƃ���Ő��������g������܂����A�������ł͏H���Ő����I
�~���H����������~������O�ɂǂ�~�ɃG�T��H�ׂ�H���ł������̂��Ĕ����Ƃ���Ă��܂��B
�܂����g���ʂ������Ȃ�A���荠���i�ƂȂ�܂��B
�܂萣�˓��ł͏H���{�I���̂��Ƃ́A�n���̎Y�n�ŗL���ȗR�ǁi�W�H���j�ł��������Ƃ������邻���ł��B
�������������̊C�Œb����ꂽ�n���́A�܂������̈��n�I
����ɂ́A���̔������������×~�ɐH�ׂ���H�ƁI
�����`�`�������͂��I
���X�ł͒��s�Ŏd���ꂽ�n����X���̊��F�ň�����z���A������Ԃɒ��߂āA�J���č�������ēX���ɕ��ׂĂ���̂őN�x�̓o�c�O���ł��B
�����������Ȃ邱�̋G�߁A�n����Ȃ�Ă������ł����B |
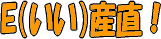
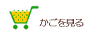 |
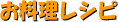 |
�i�n���̓������j
�i�P�j���肵�Ă���n�����T�p�ʂÂɐ�
�i�Q�j�����n����M���ɃT���Ɠ����i��u�j
�i�R�j�M��������o�����n����X���̒��ɓ����
�i�S�j�����Ɏ��o���A����̗l�Ȃ��̂Ő�����ďo���オ��
�i�T�j�~�����|���X�������Ղ�t���ĐH�ׂ�Ɣ��� |
 |
 |
�i�n���̎h�g�j
�i�P�j�n�����O���ɉ����āA��ɔM���������A�X���ɂ����B
�i�Q�j���ɂӂ��Ă���A�˂��̂悤�ɐ�܂��B
�i�R�j�킳�сE�|���X�E�~���łǂ����B
�i�n���̒W�H��j�S�l��
�i�P�j���肵���n����H�ׂ₷���傫���i�T�p�ʂÂj�ɐ�܂��B
�i�Q�j��o�`�����܂��B
���o�`�i���z�ƍ��Ԃ��j5�J�b�v�E�Z�����ݖ�0.5�J�b�v�E����0.2�J�b�v�E��0.3�J�b�v�E�����X�B
�i�R�j�y��Ɂi�Q�j�̓�o�`�����A�����������ɃX���C�X�����ʂ˂������āA�����Ă�����i�P�j�̃n�������o���オ��B
�ޗ��F�n���Q�{�E�ʂ˂��R��
���o�`�i���z�ƍ��Ԃ��j5�J�b�v�E�Z�����ݖ�0.5�T�J�b�v�E����0.2�J�b�v�E��0.3�J�b�v�E�����X�B |
�i�n���̓V�Ղ�E�t���C�E���g���j
�H�ɑ���1Kg���z����悤�ȑ傫�ȃn���́A���̂̂�̓o�c�O�������A�����d�����ɂ����邱�Ƃ�����B�����ł������������͓̂V�Ղ�E�t���C�E���g���A���ē��A��������Ɖ��M�����ł��闿�������E�߁B |
 |
�������n�����J���A���ꂼ�܂��ɎY�n�̋����I

���s�Ŕ��������n���́A�X���̊��F�Ɋ������Ă���


�����A���F����n����g����{�����J�ɍi�߂�


���L������邽�߂̌���


�����i�ʂ߂���Ǝ���Ă���������o��


�w��������J��
����(facebook)��������


����
����(facebook)��������
 |

�X���̔� |
�u���O
���o�̏H�i�n���ҁj
���o�̏H�A�S���I�ɂ͐V���T���}���o���y���܂��Ă����B
�u�H�T�o�͉łɐH�킷�ȁv����Ȃ��Ƃ킴������悤�ŁE�E
�����Ȃ�u�H�T�o�͕v�ɐH�킷�ȁv�H/��
�ꌹ�͂����ȈӖ�������悤�����A�T�o�̏{�͏H�A����قǔ��������Ɖ��߂��Ă������B
���ł��^�C���͂��߃A�W���ԁi�T�����j���H���{�B
�������������i�����l�Ȓl�i�j�ł��t�E�Ă̂��̂Ƃ͒l�ł����Ⴄ�B
�����āA�����炪������i������Ƃ�����E�E�ԈႢ�Ȃ��n���I
�n���͋_���Ձi���s�j�̉e�����A�Ă��{�Ǝv���Ă���l�������B
�~�i�ԈႢ�j
�~�ɔ����×~�ɃG�T��H�ׂ邱�ꂩ��̃n���i�H�n���j�́A�ہX�Ƒ����Ď��̂̂���o�c�O���ɂȂ�B��N�ōł����������Ȃ�G�߁B
����ɂ́A���g���������Ă���B
���̈���A���̂��H�u�c��n���v�ȂLjӖ��s���Ȃ��Ƃ������A�߂������Ƃɂ��܂ЂƂl�C���Ȃ��B
���R�l�i�������Ȃ�B
�u�Ă͒l�i���������ɂăC�}�C�`�A�H�͈����Ĕ������I�v
����A�Y�n�̏펯�A�o���Ă������I
�n���Œm����W�H�A�����̗��ٓ������̎����Ƀn���荞��ł���̂������������ƁB
�����A������������A�Ăɂ��̂��Ƃ��������Ƃ͂܂��Ȃ��I
�Ă͉Ă̔��茾�t���E�E/��
�{�Ƃ͐��g�������������Ȃ鎞���ł͂Ȃ��A�����܂Ŏ����̂��Ĕ��������Ȃ鎞���������B
�H���{�̋��͑����A���o�̏H�Ƃ͏�肭���������̂��B
�n���͑傫�������ǂ��H
�H�͑傫�ȃn�������B��ʓI�ȃT�C�Y�����E�����悤�ȁH�ǂł����̂�����B
�܂��́��ʐ^�������A
����ǂ���������l�i�Ȃ�A���Ȃ��Ȃ�ǂ����I�т܂��H
�u������̑傫�ȕ��v
����������l�͑����͂��B
�Ƃ��낪�A�l�ł͏�̑傫���̕��̕������l�����B
�X���ł��u�Ȃ�ł��̑傫�����������́H�Â��́H�v���ƁA�q�˂��邱�Ƃ�����B
�ǂ����Ă��̗l�Ȃǂł����n���͈����̂��H
�n���͍���������������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ݂Ɏʐ^�͍��������O�̏�ԁB
������ȏ�̑傫���i���̃n���������j�ɂȂ�ƁA�����Ŏ��̂̂�̓o�c�O���Ȃ̂����A�����d���H�ׂ�Ƃ��ɋC�ɂȂ邱�Ƃ�����B�������V�ŁA�ǂ����Ă��c���Ă��܂����Ƃ�����B
�������������̂̓t���C��V�Ղ�A���g���A�������͉��ē��ɂ͓K���Ă��邪�A��ⓒ�����ɂ͂��܂�K���Ȃ��B

�����̂̒��͑����H
�u�����͒�����������E�E�v�悭����������B
�m���ɐ��Ԉ�ʂ̋����͂�����������Ȃ��B
�u���͎d����ɂ���v�Ƃ�����悤�ɁA�d���Ƃ����̂͏��ɂ����ĂƂ�킯�d�v�ŁA
�����͒��������狣���悤�ɂ��Ďs��ɍs���A���l�i�ЂƁj���������ł��l�ł��̂��鋛�B���悤�Ƃ���B
�����ɂƂ��đ��N���͎O���̓��B
�����A���̂�����̎���͂������N�ł����Ԃ�Ɨl�ς�肵�Ă���悤���B
�����A������̏ꍇ�A�����Ă��鋛�̑����͖��Ε��i�n���j�B
����͎s��͎s��ł������s��i����s��j�ł͂Ȃ��Ȃ��A�l�̎s��i���ΉY����/�Y�n�s��j�Ŕ����t���邱�ƂɂȂ�B
11��������n�܂�Z���Ɏ���Z����ɗ����āA���t���l���Ă��������Z�����Ƃ��A
���ꂪ�L���Ȗ��̒��s�B
�����i�����j���Z����ɗ��Ƃ����̂́A�S���I�ɂ͒������P�[�X�ł͂Ȃ����낤���A
�i�ʏ�A�Z���ŋ����t����̂͒����A�����͂��̒�������d�����̂���ʓI�ȗ���j
���X�ł͕l���玝���A�������̑����́A���E���h�i�ۂ��ہj�ŕ��ׁA�����Ē��������̏�Œ�������B
���̂��߁A������͎d���Ɣ̔��A�������A�S�Ă��قڈ�Ăɓ����i�s�ōs���邽�߁A���Ƃ͂����ĕς���ĖZ�����Ȃ�B
�Ƃ��낪�n���̋G�߂́E�E
�n���͍�����������̂łȂ��ƃ��E���h�ł͔���Ȃ��B
�������ĊJ������A����Ƃ��ꂪ��ԉɂ̂������ƁA
�����Ē��������̏�ŗ�������ƂȂ�Ǝ肪�܂��Ȃ��B
�����ŁA����Ԃɂ��߂č�������ēX���ɕ��ׂ�B
�ӂ���͂������������̎d���݂����܂�Ȃ��̂ŁA�o�Ύ��Ԃ�����قǑ����Ȃ����A
�n���������Ƃ��́A����Ԃ���Z�����o�Ύ��Ԃ������Ȃ�B
|